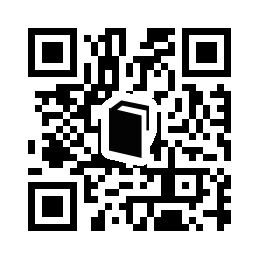ずいぶん前のことで出典も何も忘れてしまったが,江戸末期に勃興,跋扈したいわゆる侠客組織の中枢にいたのは,主に農家の次男坊,三男坊であったというのを読んだことがある。
江戸時代の農民というと武士の権力に搾取される農民というイメージが強いが,社会不安を醸し出すほどの飢饉はそうたびたびあったわけではなく,新田開発などによる食料の増産もあって人口も増えた。一部には田畑を分与するいわゆる「たわけ」という相続もあったろうが,江戸末期には受け継ぐべき土地家屋もなく,さしあたって食うには困らぬものの将来に何の展望もない若者が農村に飽和状態になっており,彼らのポテンシャルが飢饉を契機に博徒というかたちで暴発したと言えなくもない,らしいのね。
本書は,こうしたユース・バルジ,すなわち戦闘能力が高く社会にトコロをもたない青年層の増大こそがテロリズム,暴力的行動の真の原因である,という視点から,大航海時代のイベリア半島(スペイン・ポルトガル),それに続いて世界の覇権を握ったオランダ,イギリス,アメリカの歴史を見直し,太平洋戦争直前の日本の分析を経て,戦後の南米,現在のイスラーム圏までを俯瞰,暴動と人口の相関に潜む「隠れた法則」をあぶり出して見せる,なんと言いますか「目ウロコ本」であります。
ただ,ちと読んでて気になったことがあるんだよね。いや,理論と実証の説得力には脱帽するし,現在も一人の母親が生涯に7人の子を産む(確率からいうとその半分が男の子である)アフガニスタンが今後も世界紛争の火種になるだろうからタイヘンだというのも分かる。なにしろそういうトコロから出てくる兵士は母親にとって「大勢の子供の1人」であり,それを迎え撃つのは「大事な1人息子」なんだから,迎え撃つ側にはどうしても厭戦気分が蔓延する。
だけどほんぢゃどうすればいいのかっちゅうところになって,…もちろんはっきりそう書くのは避けているけれども,「平和的解決が可能だと思ってるヤツはおめでたい」,つまりは「連中をぶっ殺すしかない」という風になっていくのはどんなもんか。著者のハインゾーン氏はドイツ人なんだが,中東問題(イスラエルとアラブの問題)に対してドイツ人であるがゆえの微妙なバイアスみたいなものがそこに垣間見えるような気がする。
ついでに言うと(これはオレが東洋人だから感じるのかもしれぬが)ヨーロッパ人であるゆえのある種の「既得権は既得。先祖が暴力でぶんどったものかもしれないけど,いまこの時代にそれを暴力で取り返すってのは許されることではない」てな身勝手さも。決してオレはテロを肯定するモノではないけれど,お前らそういう態度ぢゃ結局いつまで経っても殺し合いが続くだけやないの,と思いますよ。