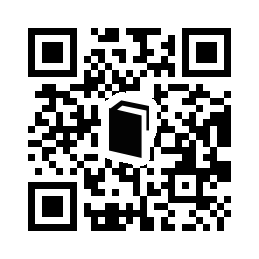「大のオトコ三人が舞台に出てきて,一人が一人につっかかり,残りの一人がつっかかった男を後ろから羽交い締めにして制止する。これだけで日本人ならそこで何が行われているか誰でも解る」。
多少言葉遣いは違うかも知れないが,上はかつて東京オペラシティで数多のジャズ・ミュージシャンを集め「ジャズ忠臣蔵」を演った際の主宰・山下洋輔の言葉である。いやホントにそうだよね。少なくとも,オレ(昭和30年代生まれ)の世代までは確実にそうだと思う。
が,実は我々は「忠臣蔵」という芝居のストーリーあるいはその後にくっつけられた有象無象については詳しくても,実際にあった「赤穂事件」については結構知らないことが多い。いや知ってるつもりなんだが,よく調べると史実にはそんなことがあったという証拠はなく,つまりは芝居の創作、のちの舞台での演出だみたいな。
この本はそういう芝居流行後に生まれた伝説(?)を排し,あくまで素の事件の記録として残された資料にあたって構築されたコトの全貌…いやそういうものなので「全貌」とまで呼べるかどうかは心もとないところもあるわけだけど現時点でのベスト,時代も新しいしいまさら始皇帝の兵馬俑みたいな大発見がでてくるような話ぢゃないし。
でまぁ,なんでも真実というのは多かれ少なかれ巷間流布しているハナシよりしょぼかったりするわけだ。
オレなんか子供の頃ポプラ社から出てたジュニア版の「忠臣蔵」つう本で,あの殿中松の廊下に至るまでどんだけ浅野内匠頭が吉良上野介に煮え湯を飲まされ口惜しい思いをしたかというのをこれでもかこれでもかと刷り込まれたクチなんだけど,基本的に500枚の畳替えとかああいう分かりやすいイジメというのはなかったんだね。
吉良に賄賂を渡さなかったから云々というのも,そもそも高家は勅使供応の指南役,今で言えばコンサルタントなんで,コンサルタント料を取るのは当然のことだし(もともと吉良家は四千石くらいの身代で,この役目は大きな財源だったはず),接待が失敗すれば指導に当たってる自分にも累が及ぶことなので,まずいことがあればきつい言い方でたしなめたりしかりつけたりもするだろうが,嘘を教えたりする理由はない。
だからやっぱり松の廊下の事件というのは文字通り癇癖のあった内匠頭がキレちゃった,ということだったというのが妥当である。それからメインテーマである大石たちの討ち入りもオレ等はなんとなく「敵討ち」と解釈してしまうが,彼らの論理では「(ことの是非はともかくとして)主君がやろうとしてできずに終わった行為(というのはつまり吉良殺しなんだけど)をまっとうするのが臣下の役目」なのね。だって切腹を命じたのは吉良ぢゃなくて将軍家だし。
ほんで艱難辛苦の末,あの雪の日の討ち入りとなるわけだけど,討ち入ったのはご存知四十七士,討ち入り後忽然と姿を消した(理由については諸説あり)寺坂吉右衛門を含めたその全員が無事吉良邸を出てるわけだが,ぢゃ吉良家側の被害はいかほどか,主人上野介が首を取られたのは確実として他に何人が抵抗し何人が殺されたか。これもちゃんと記録があるんだが(当たり前だ,平たく言えば押し込み強盗事件なんだから),その内実を知ると結構吃驚である。
結局赤穂事件というのは,荒ぶる戦国を闘った武家の思想,行動様式の残滓が,いち早く都市化され日本で一番その種の気風が希薄になっていた江戸の町で最後のあだ花を咲かせたというものだったんだなぁと。
あ,ついでに読んでて思いついたんだけど,芝居の「忠臣蔵(正確には仮名手本忠臣蔵)」は,幕府を慮って時代設定を室町時代,大石内蔵助の名前も大星由良之助とかと変えてある。題名にわざわざ「蔵」の字を入れたのは,あんまり変え過ぎてみんながあの事件のことだと気づいてくれないんぢゃないかと不安に思ったからかも知れない。んなこたあないか。