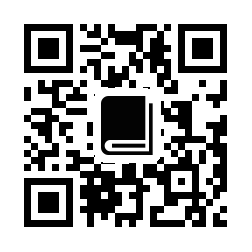題名に惹かれて手に取った本なのだが、読んでみるとこの邦題はちょっとずれてる。いや、厳密に説明されればこれでもいいのかも知れないのだけど、ここで言う「実在するか」というのはたとえば「幽霊は実在するか」とか「宇宙人は実在するか」(例示に「ダンダダン」が入ってるな)というのとはちょっと、違うのである。
著者のオキーン博士はアイルランドのダブリン大学の教授で、精神科医として30年以上のキャリアを持つ脳科学の研究者。内容は大きく二つのパートに分かれていて、前半の題名は「私たちは記憶をどのように作るか」。目、耳などの感覚器官から入ってきた情報が脳内のそれぞれの専門分野に送られ分析される。ここまでは「記憶」ではなく「感覚」だ。トランプでやる「神経衰弱」を思い浮かべよう。1枚のカードをめくった。♡のクイーンだ。ではどうやってこれを記憶するのか。
そこで重要なハタラキをするのが海馬である。河馬ぢゃないよ。「感覚」は電気信号として海馬に伝わり、ここでニューロンの接続を促し、同じような刺激に対してまとまって発火する樹状突起というものを形成する。この樹状突起の発火パタンがつまり「記憶のコード」である。同じコードが繰り返し発火することで「記憶」ができあがる…今書いてるこの「記憶に関するオレの記憶」もそうやって形成されたわけだ。
この海馬に形成された記憶パタンは所謂「短期記憶」である。形成されたときには閾値を超える発火があったはずだが、その後発火しない状態が続くと解体され、ニューロンは別のパタンの形成に使われる。逆にある頻度で繰り返し発火するパタンは、睡眠中に大脳皮質に移されて「長期記憶」となる…らしい。
こういう話も面白いのだが、オレにとって真にメウロコだったのは後半「記憶は私たちをどのようにつくるか」の方である。普段オレ達はなんとなく「記憶」と「自我」を別のものだと思っている。「自我」っていう主体があって、そいつが脳のなかから「記憶」を引っ張り出したり、忘れたりしている…と。
でもオキーン博士に指摘されて改めて気付くと、オレが「自我」だと思っているものの中身はなんと全部「記憶」なのである。一番古い記憶(三歳のとき池に落ちて祖母に助けられた)、少年時代の悔しい思い出、仲間とバンドを組んで文化祭で演奏した記憶、あんまり思い出したくない学生時代の恋愛、プログラマとして関わった、時系列で整理しないと全部は思い出せないほどの仕事の数々…オレという自我、人格はこれらの記憶から形成されており、深く考えれば考えるほどそれ以外の要素など何にもないではないか。そして、そう考える時に使う「日本語」もまた「記憶」にほかならない。
うーん、そうだったのか。だから記憶を失ったヒトが性格まで変わったりするのは不思議でもなんでもないのだなぁ。読み終ってひとつ賢くなったような気がする本である。これはなんとか「長期記憶」にしておかなければ。